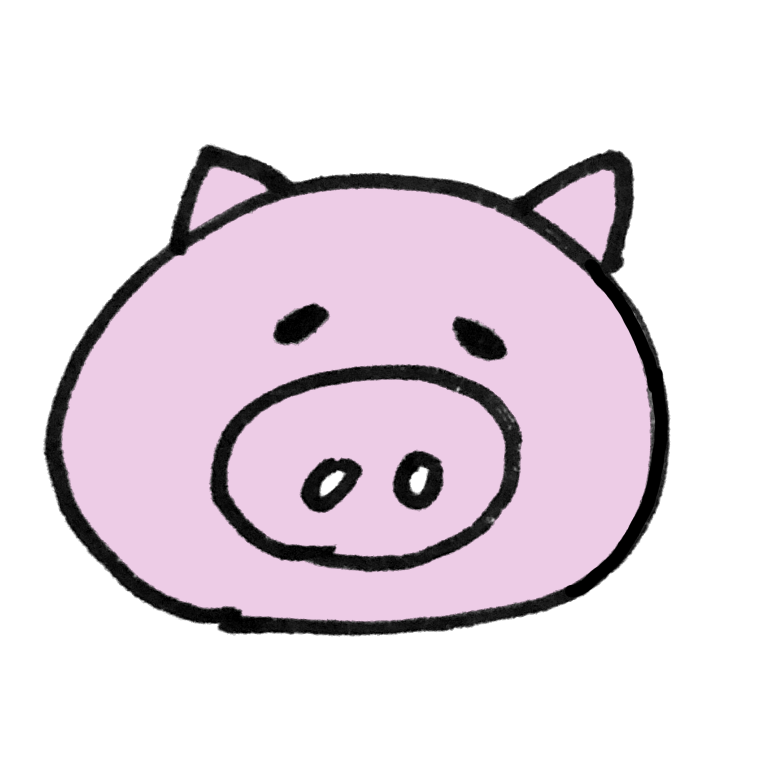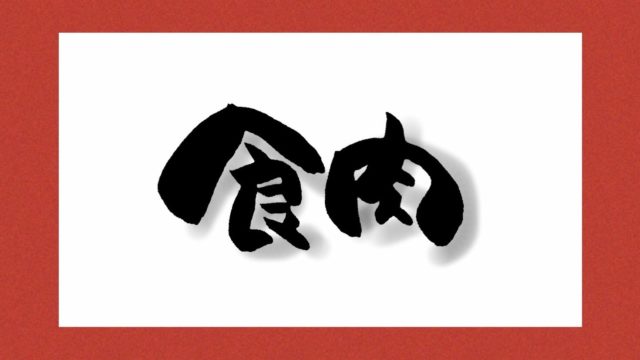みなさんこんにちは、田舎の精肉店肉処とよた略して『肉とよ』です🍖
毎日食事をする意味。
それは「生命維持に欠かせない必須の栄養素を摂取するため」と定義付けされています。
三大栄養素であるたんぱく質・脂肪・炭水化物や、無機質、ビタミンなどを体内に摂取することで、私たちの体は日々成長しています。
さて。
食肉には、人間が成長するのに必要なたんぱく質がたくさん含まれていることは、みなさんご存じだと思います。
そして、ほかにも体に役に立つ成分が豊富にあります。
しかしひとえに食肉とはいっても、牛・豚・鶏によって含まれる成分は異なるし、またその部位によっても変わります。

以前子どもたちも大好き『鶏の栄養』について肉とよ的に解説させていただきました。
今回は『牛肉の栄養』について解説していきます!
牛肉が赤い理由
お肉の色は、たんに食欲をそそるだけでなく、種類や鮮度を見分けるうえで大切な情報を持っています。
鶏肉や豚肉のピンク色に比べて、牛肉は鮮やかな赤色をしています。

これは、ミオグロビンという色素たんぱく質が起因しており、牛肉にはこの含有量が0.5%と多く含まれています。
動物の肉は、生前、血液中にヘモグロビン(血色素)によって色味がついているのですが、死後ヘモグロビンが失われていくと別の色素の影響が大きくなります。
それがミオグロビンです。
ミオグロビンはヘモグロビン同様に、酸素をたくわえる働きがあります。
そしてこの成分は運動量が多いほどに含有量が多くなるので、活発に動かす部位ほどに色味が濃くなります。
牛肉の部位でも特にカタ・モモ肉が赤いのは、酸素消費量の多い筋肉を有しているからです。
さらに、牛肉にはほかの食肉よりも多くのビタミンB12が含まれています。
ビタミンB12は、葉酸(赤血球のDNAの合成に必要な成分)の働きを助けます。
このように、ミオグロビンが豊富であり、ビタミンB12も含む牛肉には血をつくる働きがあることがわかります。
霜降りという名の脂肪
牛肉の美味しさの1つに、甘味と旨味を兼ねそろえた霜降りがあります。
この霜降りはサシとも呼ばれ、格付けをする上で「脂肪交雑」という大事な項目の1つでもあります。
‥脂肪。
栄養学的に脂肪は「生体活動に必要なエネルギーを蓄える」という重要な栄養素でもありますが、摂取量が多ければ肥満にもつながります。
もともと人間には飢餓に備えて栄養を体に蓄え、それを維持しようとする機能が備わっています。
特に和牛のカルビ肉は非常に脂肪が多く、肉の約50%が脂肪でできています。
 ほかの部位であっても、牛肉には霜降りが入っているため、豚や鶏に比べると脂肪の含有量が多く、カロリーも高いです。
ほかの部位であっても、牛肉には霜降りが入っているため、豚や鶏に比べると脂肪の含有量が多く、カロリーも高いです。
さらにいうと、先ほど説明したミオグロビンには鉄も含まれており、この鉄は、野菜などに含まれる遊離鉄(ほかの物質と結合しない鉄)に比べて、体内に吸収されやすいのが特徴です。
肥満が気になる場合は、脂肪分の少ない部位を選んだり、脂肪の摂取が少ない調理方法を選ぶなど、食べ方を工夫すると良いでしょう。
脂肪の分解をうながす
しかしご安心を!
牛肉にはカルニチンが豊富に含まれているという特徴もあります。
このカルニチンは脂肪の分解を促進し、エネルギーに変える働きを持ちます。
そのほかにも牛肉にはいろいろな効果が認められており、
- 共役リノール酸‥体脂肪減少効果
- オレイン酸‥LDLコレステロールの減少・酸化抑制効果・血液降下作用
といった成分もあります。
このように、食肉のなかにも脂肪を分解する力のある栄養素が豊富に含まれているのです。
まとめ
牛肉はほかの食肉に比べて霜降りが多くカロリーも高めですが、その分体を動かすために必要な成分も豊富です。
持久力を必要とする時や、特にスポーツをする人には、ぜひとも摂取してほしいお肉でもあります。
牛肉で健康的な身体づくりをされてみませんか(^^)??
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。